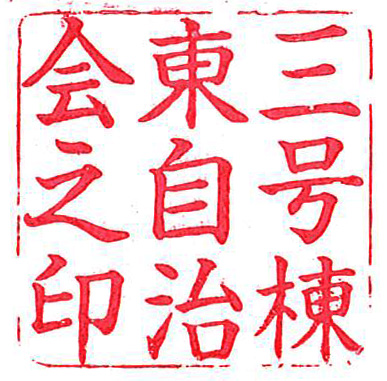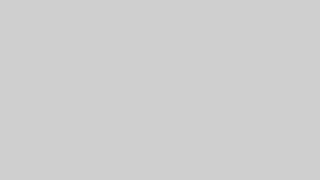1. 自治会共益費とは
当団地に入居している世帯は、自治会共益費を必ず支払わなければなりません。支払いを拒否した場合、法律によって処罰されることになります。任意の自治会、町内会活動と混同しており「加入は任意なので支払い義務はない」と間違った解釈をしている人がいる可能性がありますが、完全に合法である理由は次のとおりです。
自治会共益費を支払うことが義務である合法的理由
①公営住宅法、東京都条例に明示されている
②使用用途が法律にて示したものに限定されている
③会則にて使用用途が明示されている
④使用した共益費の会計情報が明示されている
⑤徴収する金額に合理的な根拠がある
2. 公営住宅の維持管理について
私たちが住んでいる都営柳沢6丁目アパートは地方自治体(東京都)が管理している公営住宅です。3号棟は都営住宅と都民住宅が合わさった複合住宅です。UR都市機構が管理しているUR住宅、不動産管理会社が管理している集合住宅、管理組合が管理している分譲マンションなどとは性質が異なります。
公営住宅の場合、共用部分の維持管理を住民たちで行わなくてはならないという法律、条例があります。
【公営住宅法 第27条 入居者の保管義務等】
公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
【都営住宅条例 第22条 使用者の保管義務】
一般都営住宅の使用者は、当該一般都営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
共同施設について必要な注意を払い、正常な状態を維持するとことは?
共同施設は、みんなで使う場所や設備(例: 廊下、エレベーター、ゴミ置き場など)のことです。これらを安全で快適に使えるように、注意深く扱い、壊れたり汚れたりしないようにきれいな状態を保つ必要がありますということです。
3. 管理方法について
公営住宅を維持管理する方法は次の二つに分けられます。
【自主管理】
内容:
住民皆で協力して、掃除や電球の交換、駐輪場の管理や草刈りをやっていく
メリット:
管理費がかからない
デメリット:
管理業務のために時間的に拘束される
【委託管理】
内容:
住民から管理費という形で費用を徴収して、外部の管理会社へ委託する方法
メリット:
管理のための時間から解放される
デメリット:
管理費がかかる
自主管理にするか、委託管理にするかによって管理費が大きく変わってきます。都営住宅を募集している管理会社であるJKKのホームページにも次のように明記してあります。
共用部分(廊下、階段、敷地、集会所、ごみ置場等)の維持管理は、入居者の皆さまが共同で行っていただき、これにかかる費用(電気・水道・ガス料金、清掃業者への委託金等)は入居者全員が負担して入居者の代表者(自治会等)を通じてそれぞれの事業者へお支払いいただきます。この費用は住宅によって異なりますが、1ヶ月1世帯約2,000円から5,000円程度かかります。
補足:
エレベーター等の共用設備及び合築等により他の施設と一体的に管理する共用施設は、東京都が入居者に代わって維持管理を実施します。この維持管理にかかる費用は、共益費として使用者負担額と同時に東京都へお支払いいただきます。
4. 公営住宅に自主管理が多い理由
公営住宅は基本的に、所得の少ない方のための住宅です。URや民間の住宅と同じように管理業務を外部に委託するとしたら、委託費用が発生します。管理費用は一般的に家賃の5~10%が相場と言われています。公営住宅の家賃にあたる使用料には、所得に応じて補助があり、所得に対して10~70%が減免されています。
しかし支給される補助金は減額される前の使用料(家賃)に対してのみ適用され、管理費に対しては適用されません。もし管理業務を他の集合住宅のように委託するとしたら、次のようになってしまいます。
通常使用料:
87,000円
管理費:4,350円
管理費負担率:5%
補助(30%)を受けた使用料:
61,100円
管理費:4,350円
管理費負担率:7.1%
補助(65%)を受けた使用料:
30,700円
管理費:4,350円
管理費負担率:14.1%
管理費負担率が実際に支払う家賃に対して変化してきてしまいます。
補助の割合は所得が少ない世帯ほど大きくなります。つまり所得に対しての管理費の負担率は使用料に対してのものよりも高くなります。したがって必然的に、公営住宅では住民の負担を減らす代わりに、住民皆で協力して共用部の維持管理をしていき管理費負担率を減らそうという流れになります。
また自治体から支給されている住宅補助の原資は税金です。管理費に対しても補助する(税金を使う)ことは納税者からの反発が起こる可能性が高く法律や条例の改正は困難です。
5. 自主管理にかかる時間コスト
私たちの自治会においても過去には、住民全員参加型で維持管理をしていました。しかし2020年の新型コロナ発生時期に住民間の接触を避けるために制度を大きく見直しました。
では維持管理に果たしてどのような内容と各世帯がどれくらいの時間を負担していたのか概算を算出します。(世帯数は現在と同じ110世帯で算出)
| 内容 | 詳細 | 時間 |
| ①ごみ置場、B1エレベーターホール清掃 | 毎日交代で行い、1回あたり1時間と想定 | 365時間 |
| ②外回りの掃き掃除、雑草除去、不法投棄処理 | 全体清掃として月に1度1時間(1月、8月は除く) | 1100時間 |
| ③各階の共用部分の清掃 | 週ごとに交代で各階の共用部を清掃(1回30分ほど) | 260時間 |
| ④自治会を集会(役員会)の実施 | 各フロアから1名代表して役員として参加して、月に1度1時間ほどの役員会を実施 | 120時間 |
| ⑤役員としての活動 | 役員会とは別に、それぞれに役職をつけて1年間活動 | 120時間 |
他にもまだあると思うが、概算するとこのようなります。合計1965時間で1世帯あたり17時間の負担となる計算です。
6. 管理活動に参加できない場合の対応
「5. 自主管理にかかる時間コスト」で示した管理活動に参加することができない理由は、世帯によって様々です。仕事の都合、体調などの都合で活動に参加できない場合があります。しかし、当時の東会の仕組みとして、不参加者が発生することに対しての対処法がされていませんでした。
一般的な場合の不参加の場合の対処法は主に次の4つになります。
| ① 代理人(親族、関係者、隣人など)に代わりに行ってもらう |
| ② 違約金を支払って免除してもらう(多くの場合は1時間あたり1000円) |
| ③ 皆で助け合っていこうという善意に甘えて免除世帯にしてもらう |
| ④ 無視して活動に参加しない。バックれる |
7. 過去に全体清掃を廃止、清掃業務を委託した経緯
東会では違約金は徴収していませんでした。そのため「6. 管理活動に参加できない場合」の対応の3~4の割合が増えていきました。
中には体調が優れずに、参加することができないことに対して心苦しく思っていて、違約金を支払いたいという意見もありました。しかし多くは4の「無視して活動に参加しない」方が増えてきました。真面目に清掃活動を行っている人たちに負担を生じさせる「正直ものが損をする」仕組みに成り下がってしまいました。原因は住民の家族構成の変化、高齢世帯の増加による部分が大きく影響しています。
そこで総会にて次の3つの案で住民投票を行いました。
今後の全体清掃活動、個別の清掃活動について
① 全世帯から均等に費用を徴収して業務を委託する(決定)
② 参加しない人から違約金を徴収する
③ 現在の状態を放置
のいずれかで議決をとったところ1で決定して業務を委託することに決定して現在に至ります。
「③各階の共用部分の清掃」だけは残して現在に至っています。
8. 管理活動に参加できない場合の違約金について是非
議決をとるときに、一部の意見として「違約金を徴収することは正しいのか。なぜ違反したわけでもないに徴収されなくてはならないのだ」という意見がありました。公営住宅に住んでいる以上、共用部分の維持管理することは絶対条件です。したがって、住民全体で清掃をする業務に対して参加しないことでペナルティとして違約金を徴収することは法的に全く問題ありません。違反した場合は公営住宅法違反になり、自治会からは損害賠償請求、地方自治体(東京都)からは明け渡し請求される行為に該当します。
公営住宅の明渡し
公営住宅法第32条 事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。
①不正入居
②家賃滞納(3ヶ月以上)
③住宅・共同施設の故意毀損
④入居者の保管義務違反
⑤管理条例違反
⑥借上げ公営住宅の期間満了
9. 現在の清掃活動状況
・外部の清掃活動、不法投棄物対策
毎朝、日中にボランティアで掃き掃除やごみ拾い活動をしてくれる方がいるお陰で、環境美化が保たれています。しかし、ボランティアの方々の生活変化、転居などでいつそれが無くなるかどうか分かりません。清掃活動を委託、もしくは全体清掃を再開できる準備はしておくべきです。
ボランティアの語源:志願兵
国や社会のために、自らを犠牲にして行う行為のことです。自分が楽をしたいから、命が惜しいからという理由でボランティアに期待することは許容されません。
・各フロアの清掃活動
各フロアで札を回したりして、交代で行っています。ただし、業務をせずに札だけを回しているケースもあり得ます。理由は体調が優れないなど様々だと思われますが、面倒臭いから、楽をしたいから、何も言われないからという理由で業務をしない場合もあり得ます。廊下の排水口に埃やごみが貯まりやすく、万が一上下の排水部分に溜まって塞いでしまった場合は漏水の恐れがあります。
また、団地が30年を経過したことで劣化が今後さらに進みます。色々なところに破損や異変が発生することが予想されます。その時に、修繕の対応を迅速に行うことも重要になります。
10. 今後の清掃活動対応について
・外部の清掃活動について
ボランティアに頼らなくても済むように定期的な清掃活動は継続していきます。
・各フロアの清掃活動
法律を遵守して、清掃を行っている人が損をしないような仕組みが必要です。あらかじめ全員から違約金を徴収しておき、清掃業務をしてくれる人に再分配する方が合理的です。
11. 想定される意見
・月1000円の根拠が欲しい。また1000円が高い気がする。
業務内容と必要労務内容と時間は「4. 自主管理にかかる時間コスト」にて示したとおりです。維持管理業務に示したトータル労務時間は1年間で1965時間にのぼります。
東京都の最低時給が1163円、清掃業務の平均時給が1268円です。
最低時給で計算:228万円
清掃の平均時給で計算:249万円
となります。
1000円を110世帯で徴収した場合、1年間で132万円になります。
現在東京都に草刈りを委託しており、世帯あたり月約500円の負担となり、合計66万円の負担となります。
この二つを合わせると198万円になります。
しかも、この負担金には排水管清掃業務、清掃用の備品購入費用も含まれている金額です。
したがって、月に1000円の住民負担は決して高額ではありません。
・生活が厳しく、値上げされると厳しい
各フロアの清掃業務の委託先を住民優先にて考えております。これまでと同じように清掃活動行ってくれるならば、協力金を支給するようにします。清掃活動をすることで、値上げ分が相殺される、もしくは余剰金を受け取ることができるような仕組みを目指します。
自治会共益費が現在でも厳しい。12,000円になったら、一括して支払うと当月の生活費が厳しい
共益費の支払い方法を一括、分割と選ぶことができ、かつ支払い期限を半年後に設定します。清掃業務の協力金も同時に支給するようなスケジュールとすることで、キャッシュフローが厳しくなることを防ぎます。
仕事が忙しく、清掃業務をする時間がない
違約金を事前に支払ってもらうことで、清掃活動からは解放されます。自治会活動に時間をとられるよりも、空いた時間をビジネスや趣味に活用した方が、幸福度が高まる方は多くいるはずです。
月に1,000円支払うことで、外回りの掃除、各フロアの掃除、ごみ置場の掃除からも解放されるのであれば喜んで支払うひとは多いと思います。お金を稼ぐ方法を持っている人にとっては圧倒的にメリットが大きいです。
近隣自治会は自治会費がもっと安いのでは?
月額の自治会費が極端に安い自治会は住民全員参加型、かつ不参加者から違約金を徴収して平等を保っている可能性が高いです。そうでなければ、活動している誰かの犠牲のうえに成り立っている、もしくは過去に徴収したプール金があるなどです。しかし環境が変化することでいつ崩壊してもおかしくない仕組みであると言えます。
例):毎月自治会共益費 100円、全体清掃不参加違約金(1回):1000円、役員免除金:5000円など
会計情報を見れば、内訳がわかると思いますので、ご自身で取り寄せて見てください。
会費100円だけだと年間132,000円しか集まらず、排水管の清掃に約35万円かかるので非現実的。プール金があったとしてもいずれは枯渇するか、排水管の清掃ができなくなる。
昔のように全員参加型に戻したい
是非、東会の会長や役員業務を行って議案を提出して昔に戻してください。おそらく違約金を徴収することになり、集金業務などで住民負担が大きく増えることになりますが、現在の会長は喜んで役職を譲ります。
体調が優れず業務を行うことができない。支援者もおらず、生活費も厳しい
月に1000円の負担が厳しいということはあり得るのか疑問。
全員参加型の頃から、業務を無視し続けてきて他人の活動にタダ乗りしてきたとしか思えない。もしくは過去の住民が負担していた内容や公営住宅の仕組みを理解していないとしか思えない。
各フロアの清掃業務を行った場合、どのように報酬は支払われるのか?
まずは、清掃業務を引き受けてくれる人がどれくらいいるかどうかの調査を行ってから支払い方法などの詳細を決定します。不正が起きないようにする仕組みを構築する必要があります。
役員会とは切り離した「清掃チーム」のような団体を設立し契約書を締結すべきです。住民内に引き受けてくれる人がいなくなった場合に備えておくべきです。
全体清掃についてはどうなるの?
現在はボランティアの方々が取り組んでくれているので、そこまで汚れておりませんので、無理に実施する必要はありません。しかし、住民間のコミュニケーションの場として残したいので定期的には実施していきます。実施頻度は月に1度を考えております。
自由参加にして、金銭報酬ではなく過去と同じようにごみ袋を参加賞として進呈することを検討します。