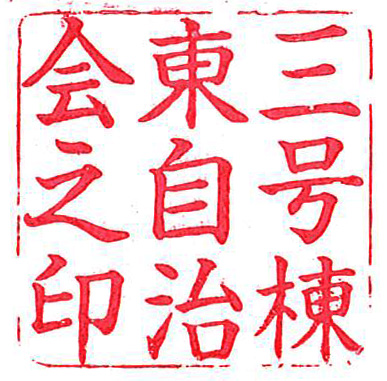経緯
2025年10月3日( 金)に開催された集会にて次の様な意見が出ております。
ごみ置場清掃を委託している方より「ごみ未分別の基準」が厳しすぎる。毎日のように回収されていないごみ「特にプラごみ」があり、回収されなかったごみは不燃ごみとしてまとめて出している。高齢世帯が増えているため、ちょっとした違反ですら未分別とされると今後さらに回収されないごみが増える可能性がある。この辺りの西東京市の見解を聞きたい。
西東京市への質問
西東京市廃棄物減量等推進審議会(第2回)
日時:2025年10月21日(火) 14:00〜
場所:エコプラザ西東京
質問1. 分別基準の厳しさについて
市民から、「分別があまりにも厳しすぎるのではないか」という声が上がっています。
たとえば、プラスチックごみに紙が1枚混入していただけで回収されなかったり、お茶漬けの袋をプラごみとして出したところ、回収されなかった事例があります。
(お茶漬けの袋はカップラーメン同様、一般的には紙素材ですが、一部具材部分にプラ素材が使われていることがあります。)
23区や海外のリサイクル先進国では、ある程度の分別でも回収を行い、回収後に工場で分別する方式を採用しています。こうした国々では、分別の「精度」よりも「参加率」や「効率」を重視しています。住民に細かい分別を求めすぎると排出率が下がるため、 「多少の混入は機械で除去すればよい」という発想で運用されています。その結果、機械化コストは上がるものの、回収率やリサイクル率は安定しています。(詳細は分別例を参照)なぜ西東京市では、ここまで厳格な分別を求めているのでしょうか。
質問2. 住民の意識づけについて
「分別の厳格化は住民の意識向上につながる」との考えもありますが、つまり1の海外が重視している合理性よりも、そのようなものよりも「ルール違反は許さない」という意識という感情を重視するという考えでしょうか?もしくはいくつかの代替案をそもそも選択肢として排除しているなど。
質問3. 未分別ごみのチェック体制について
未分別のごみを回収しない、あるいは点検する際の基準について、以下の点をお伺いします。
回収職員に、郵便局などで行われるような「ノルマ制度」的な指標や評価制度は存在しますか?
それとも、回収担当者の個人的な使命感や裁量によるものでしょうか?
「工場での分別を容易にするため」との意見もありますが、現状の運用では結果的に二重チェックとなっており、むしろコスト増につながるのではないでしょうか。
質問4. 集合住宅について
特に集合住宅では分別後の管理を特定の住民が担うことが多く、意識づけよりも負担が増しているのが実情です。この点について、市はどのように考えていますか。個別回収を中心に考えているため、集合住宅のことは考えていないなど。管理組合に任せているなど。
質問5. 氏名記載についての個人情報保護上の懸念
一部で「ごみに名前を記載すべき」との意見もあるようですが、ごみの内容から世帯を推測できる場合もあり、個人情報の流出につながるおそれがあります。行政として、氏名記載を推奨することは適切と言えるのでしょうか。ごみの内容=世帯情報という関係性を踏まえた上で、市としての見解をお伺いします。
世界の分別例
ドイツ(一部地域)
ドイツは分別が厳しい国として知られていますが、近年は都市部を中心に機械による後分別設備(自動選別ライン)が導入され、住民側の分別を簡略化する動きも見られます。ただし、州や自治体によって運用は異なり、地方では依然として細かい分別を求める地域もあります。
スウェーデン
ごみの多くを熱回収(焼却発電)に利用しており、燃やせるものはすべて可燃ごみとして回収します。プラスチックや紙の再資源化分別はありますが、他国に比べると住民負担の分別は少なめで、回収後に施設で光学センサーや風力分別機を使って選別します。
ノルウェー
ごみ袋の色でざっくり分ける方式(例:緑=生ごみ、青=プラごみ、白=その他)を採用。その後、工場で自動光学識別機械により分別を行います。居住者はほぼ「袋の色で分けるだけ」で済みます。
スイス(都市部)
各自治体で分別ルールは異なりますが、都市部では混合リサイクル回収(Mixed Recyclables)を導入しているところもあります。プラ、金属、紙などをまとめて回収し、選別施設で自動仕分けを行います。
アメリカ
「Single-stream recycling(単一流リサイクル)」が主流。 住民はプラ・紙・金属などをひとつのリサイクル容器にまとめて出す。回収後、リサイクル施設(MRF: Materials Recovery Facility)で自動分別機械によって素材ごとに仕分けされます。この方式は分別ミスが減り、回収率が上がる利点があります。
オーストラリア
各家庭に3〜4色のビン(一般ごみ・リサイクル・有機物など)を配布。リサイクルビン内は混合でもOKで、工場で自動分別。「市民がざっくり、工場が精密に」という考え方。